おひるねこ ― 2011年05月03日 22時14分54秒
シボレーカマロ LT RS ― 2011年05月04日 23時58分04秒
4月29日に納車されたシボレーカマロLT RS
日本には元々上位グレードのRSクラスが入ってきているので、オプションで追加する物は殆ど無い。
オプションで付けたのはフォグランプ。工賃込み84,000円。
日本には元々上位グレードのRSクラスが入ってきているので、オプションで追加する物は殆ど無い。
オプションで付けたのはフォグランプ。工賃込み84,000円。
それにcarrozzeriaカーナビ。バックモニター付き。地デジチューナーにETCもセットで、工賃込み386,610円。
もっと安い工賃込み20万円位のバックモニター付きポータブルナビも有る。
音で知らせるバックセンサーは標準装備。
バックモニター画面、モザイクの部分はナンバープレートが写っている。ワイセツ画像ではない。ギヤをバックにすると自動的に切り替わるので便利だ。
ドアシールプレート。左右で18,900円だが、おねだりして無料で付けてもらった。
オプションで付けたのはこれだけ。これ以外は全て標準装備になっている。
アメリカ仕様では日本の基準に合わなかった部分があるらしい。
日本仕様車で変更されている点は以下の通り。
前と後ろに有るシボレーのエンブレム。アメリカ仕様車には周りの枠が無い。
角がかなり鋭いので危険だから付けたのか?
黄色いハザードランプ。アメリカ仕様車は赤いテールランプで兼用しているらしく、コレが無い。
日本では方向指示器ランプは前後側面全て、橙色と決められている。
後ろ側面のランプもアメリカ仕様車は赤い色を使っているが、日本仕様はオレンジ色。
ただ、車両側面のランプはライトを点けた時常に点灯しており、ウィンカーの役割はしていない。アメリカでは車体側面の方向指示器の設置義務が無いが、日本では必要なので、ドアミラーウィンカーを車体側面の補助方向指示器として利用している。アメリカ仕様車のドアミラーにウィンカーは付いていない。
ドアミラー。アメリカ仕様では固定されているが、日本仕様は下の写真のように折りたたみ式になる。ただ、この折りたたみは電動ではなく手動!
タワー式立体駐車場に入るときは、係りの人に右側のミラーを畳んで貰うのか?
アメリカでは固定されているというのも凄い!
中のミラーは電動で動かせる。
タワー式立体駐車場に入るときは、係りの人に右側のミラーを畳んで貰うのか?
アメリカでは固定されているというのも凄い!
中のミラーは電動で動かせる。
スピードメーター。アメリカではマイル表示だが、日本仕様はメートル表示km/hに変えてある。
日本仕様はハンズフリーの電話機能が使えない。スイッチは残されているのだが、機能しない(一番左のスイッチ)。右2つのスイッチはオーディオ・ラジオの調整用。
日本仕様車もハンドルは左側にある。右ハンドル車は存在しないらしい。
ウィンカーを点けようとしてワイパーを廻してしまう。
使い勝手や燃費等についてはまた後日。
追記:5月16日の最終編まで8回に亘る報告になってしまいました。飽きずにご覧ください。
シボレーカマロ ライト編 ― 2011年05月06日 22時00分57秒
正面から見たオレンジ色のランプはターンシグナル(ウィンカーとハザードランプ)。
ヘッドライトはHIDプロジェクションランプ。
BMWでお馴染みになったエンジェルリング(イカリングと言う人もいる。イカリングフライみたいだからか?)がポジショニングランプ(スモールライト)になる。
フォグランプは前述のようにオプション。
ライトの点灯は基本的にオートになっている。屋内駐車場でエンジンをかけるとライトが点いてしまう。恥ずかしいのですぐにOFFにするのだが・・・
少し暗い所でリモコンでドアロックを解除しても点灯する。
なぜか、車外からリモコンでエンジンをかけると昼間でも点灯するのである。
ライトの点灯スイッチはハンドル付け根のすぐ左側にある。右の小さいダイヤルはインストルメントパネルの照度調節。これも基本はオートになっている。
少し暗い所でリモコンでドアロックを解除しても点灯する。
なぜか、車外からリモコンでエンジンをかけると昼間でも点灯するのである。
ライトの点灯スイッチはハンドル付け根のすぐ左側にある。右の小さいダイヤルはインストルメントパネルの照度調節。これも基本はオートになっている。
写真右下のレバーはハンドル位置を調整する為の物。
テールランプ(ブレーキランプ)は初代カマロを髣髴させる、レトロな感じ。
ナンバープレートの左右の白いのがバックランプで、その下のオレンジ色が方向指示器(ウィンカー、ハザードランプ)。アメリカ仕様車にはこのオレンジランプが付いていない。
テールランプ(ブレーキランプ)は初代カマロを髣髴させる、レトロな感じ。
ナンバープレートの左右の白いのがバックランプで、その下のオレンジ色が方向指示器(ウィンカー、ハザードランプ)。アメリカ仕様車にはこのオレンジランプが付いていない。
バックセンサーがバックランプのそれぞれ左右に計4個付いている。バックカメラはナンバープレートのすぐ上に隠れている。
つーびーこんてぃにゅー!次回に続くのである。
シボレーカマロ タイヤ編 ― 2011年05月07日 08時16分55秒
タイヤはPIRELLIのP ZERO。
前輪はP245/45R20。タイヤ幅245mm、扁平率45%の20インチタイヤだ。
後輪はP275/40R20。タイヤ幅が275mmと幅広になる。扁平率は40%。
車体は全幅1915mm。全長4840mm。全高1380mm。ホイールベースは2855mmである。
ホイールベース(前輪と後輪の間隔)が長い為か小回りは利かない。最小回転半径は公表されていないが、6メートルを超えるだろう。
ハンドリングもあまり操作性が良いとは言えない。今までの車が15インチホイールだったので、大きいタイヤに感覚が慣れていないせいもあるかもしれないが・・・
まあ、昔から直線番長と言われるアメ車なので、こんなものかもしれない。
左ハンドルなので、ウィンカーとワイパーの操作レバーが左右逆なのだが、これにはすぐに慣れた。ハンドルのドア側の手でウィンカーを操作するという感覚が身に付いているのかもしれない。
右ハンドルのフランス製マニュアル車にも試乗したが、左ハンドルをそのまま右に移行した為、右ハンドルなのに左手でウィンカー操作とシフトレバーの操作をしなくてはならない。感覚的に馴染まないし左手が忙しくて仕方ないのですぐに却下した。
ただ、この車、視界が非常に狭いのである。当然、死角も多い。
コレについては又、後日。
右ハンドルのフランス製マニュアル車にも試乗したが、左ハンドルをそのまま右に移行した為、右ハンドルなのに左手でウィンカー操作とシフトレバーの操作をしなくてはならない。感覚的に馴染まないし左手が忙しくて仕方ないのですぐに却下した。
ただ、この車、視界が非常に狭いのである。当然、死角も多い。
コレについては又、後日。
シボレーカマロ 視界編 ― 2011年05月08日 15時57分57秒
フロントウィンドウの上下の長さが短いので、停止線で停まっても前の信号が屋根に隠れて見えなくなる時がある。
ボンネットの影になって下のほうも見えにくい。運転席が電動で上下するので調整は簡単なのだが、あまり上げ過ぎると天井が低いので乗り降りが大変になる。
ルームミラーもかなり視界を邪魔する。
ドアミラーは大きめで見やすい。ただ、その分Aピラーと併せての死角が増える。
運転席から見た右側の視界。右前にいる小さい子供などは見えないことがあるかもしれない。充分注意が必要だ。
バックをする時に右後方を見ても殆ど見えない。全体的に窓が上の方にある。
運転席から振り向いて真後ろを見る。窓が小さい。
リアシートに座って右側の窓から景色を見る。センターピラーもかなりしっかりしている。リアピラーもゴッツイので、視野は狭い。やはり、基本的にツーシーターなのだろう。
ただ、後ろの座席に座るとかなりゆったりしている。シートが広いのがいい。
後ろの座席から前方を見る。左右のシートの間が開いているので、視界は広がって見える。
この車、バックモニター(オプション)が無いと、バックの時の安全確認が難しいのではないだろうか・・・
シボレーカマロ HUD編 ― 2011年05月10日 19時43分47秒
HUD(ヘッドアップディスプレー)が標準装備になった。
視線を移動する事なくスピードや回転数が認識できるのでとても便利だ。
スピードメーター、外気温、トランスミッション位置、タコメーター、ターンシグナルやハイビームの表示が、3種類の切り替えでパターンを変えて投影される。
また、ラジオ局やCDトラックが変わるたびにその情報が一時的に表示される。
緊急の車両情報や警告も一定項目のみだが、表示する。
HUDコントロールは、ハンドル(ステアリングホイール)の右側で行う。
ダイヤルを右に廻すとスイッチが入り明るさの調節が出来る。
ボタンを繰り返し押すことで表示内容の切り替えが出来る。
画面位置の上下調節は、HUDと書かれたスイッチで行う。
HUDの画面は運転席の正面位置以外からは見えないので、誰も知らない密かな楽しみになってしまう。・・・・・なんだか暗いナ
カマロ エンジン・トランク編 ― 2011年05月11日 19時23分38秒
この車のエンジンはV型6気筒DOHC3.6L。最大出力227kw(308PS)/6400rpm。トルクは370N・m(37.7kg・m)/5200rpmである。
ガソリンはレギュラーを使う。ガソリン代が高い時代なのでありがたい。
V8 6.2Lエンジンの上位車種があるが、日本の道路では持て余してしまう。
3.6Lでも、長時間渋滞にはまるとラジエーターの液温がどんどん上昇してしまうのが目に見えて分かる。
6速オートマチックトランスミッションだが、加速もこれで充分だ。
シフトレバーをMの位置にするとマニュアルモードになる。
ステアリングホイール(ハンドル)の後ろ、中指か薬指で操作できる辺りにボタンがあって、ハンドルを握ったまま右手側をタップすることでシフトアップ、左手側タップでシフトダウンをする。
ステアリングホイール(ハンドル)の後ろ、中指か薬指で操作できる辺りにボタンがあって、ハンドルを握ったまま右手側をタップすることでシフトアップ、左手側タップでシフトダウンをする。
シフトレバーをMにしてタップ操作をしなければスポーツモードになる。高いギアに切り替える時間を遅延させるので、力のある走りをする。
3.6Lでも持て余し気味の私なのである。
前を開けたので後ろも開けてみよう。
トランクルームの開口部は極端に狭い!おちょぼ口。
中はかなり広いのだが、これで荷物が入れられるのかって感じ。
後部座席のシートを前に倒して、座席側から入れた方が入るかも・・・
3.6Lでも持て余し気味の私なのである。
前を開けたので後ろも開けてみよう。
トランクルームの開口部は極端に狭い!おちょぼ口。
中はかなり広いのだが、これで荷物が入れられるのかって感じ。
後部座席のシートを前に倒して、座席側から入れた方が入るかも・・・
ドアの裏にある蛍光黄緑色のレバーは、トランクに閉じ込められた時の脱出用レバーだそうだ。
誰がトランクに閉じ込められるような事をするんだ?アメリカ人って、車のトランクに入るのが好きなのか?
なぜか、バック・ツー・ザ・フューチャーを思い出してしまった。
誰がトランクに閉じ込められるような事をするんだ?アメリカ人って、車のトランクに入るのが好きなのか?
なぜか、バック・ツー・ザ・フューチャーを思い出してしまった。
カマロ オーディオ・エアコン ― 2011年05月12日 22時18分08秒
オーディオ関係の切り替えや各種設定はインフォテインメントシステムで行う。
8列×2段で16個並んだボタンと左右の小さいダイヤルでオーディオ関係や各種の設定が出来る。
下の大きい丸いダイヤル2つはエアコンの設定。エアコンの入切はオートではない。
その間の四角い中にはハザードランプのスイッチとドアロックのスイッチがある。
オーディオの外部入力は、USBとピンジャックがセンターコンソールに装備されている。同じ場所に電源ソケットが用意されているのが嬉しい。
上の丸いのが12V電源。USBにはipod用のコード(白いの)も差せる。その下に3.5mmステレオピンジャックがある。コンソールボックスなので蓋付である。
上の丸いのが12V電源。USBにはipod用のコード(白いの)も差せる。その下に3.5mmステレオピンジャックがある。コンソールボックスなので蓋付である。
四連メーター。
エンジン油圧、エンジン油温、冷却液温度、トランスミッションオイル温度がひと目で分かるようになっている。
異常が起きた時は運転席正面のDIC(ドライバーインフォメーションセンター)に警告メッセージが出るので、デザイン的要素のほうが強いのだが、あると安心感が持てる。
初代カマロを意識したオールディーなデザイン。
シボレーカマロ 最終編 ― 2011年05月16日 19時25分01秒
ハンドルには左手側にクルーズコントロールのスイッチがある。
アクセルを踏まなくても設定した一定速度で走行してくれるので、高速道路では便利だ。
只、一般道路で使うことはまず無い。
前の車にも標準装備で付いていたので、アメリカでは頻繁に使う機能なんだろうか。
シフトレバーの後ろ側にドリンクホルダーが2つ。その後ろ側はセンターコンソールボックス。青く光っているスイッチがなんだかよく分からなかったのだが、購入時にフォグランプのスイッチだと言われたのを思い出した。
オプションだからか、オーナーズマニュアルにも載っていない。
運転席の調節は座席横のレバーを使って全て電動で行う。
座席の前・後・上・下、座る部分の角度を前のレバーで、背もたれの角度は後ろのレバーで調節できる。
運転席側ドアのスイッチ。
右上がドアミラーの角度調節。
その下が窓の開閉。
左下の小さいボタンはトランクを開けるボタンになっている。
最後に燃費の話。
一般道と高速道を織り交ぜながら、日常生活よりもちょっと高速使用が多いかなという感じで、リッター6.7kmでした。
高速道路だけだと新宿から千葉県君津まで約63kmで計測したらリッター11.1km。
一般道だけだとリッター6km前後になる。
高速道路では100km/h超位で走っても、購入時から今日迄の平均速度が24km/hなので、日本の道路はいかに渋滞や信号待ちが多いかが実感できる。
海ほたる・九十九里浜 ― 2011年05月18日 15時52分25秒
昨日は夕方から雨の天気予報だったが、房総半島までドライブを強行。
房総半島だけど、暴走はしていないつもり。
帰宅したのは24時を廻っていた。車がカボチャにならなくて良かった。
三鷹を10時半頃出発して、高井戸から首都高速に入る。
レインボーブリッジを渡って湾岸線に入り、東京湾アクアラインの「海ほたる」で休憩。
東京湾アクアラインというのは、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ15.1kmの長さの自動車専用道路。川崎側の基点から9.8km地点にある海ほたるPAまでは海底トンネルになっており、海ほたるから海上に出て、木更津側は4.4kmに渡って東京湾上の橋になる。
海ほたるは東京湾に浮かぶパーキングエリアの名称である。
青く発光する体長3~3.5mmの甲殻類「ウミホタル」に由来する。
1階は大型車駐車場、2階は木更津方面からの車の駐車場、3階は川崎方面からの駐車場、4階・5階がレストランなど観光施設になっている。
1日ここで遊んでUターンして帰る人も多いという。Uターンの場合は片道料金になる。
5階の「木更津食堂」でお昼を食べた。
海鮮丼とうどんのセットで1780円。美味。
ここはPAだけあってアルコール類は無いが、キリンフリーが380円。
海を見渡せるレストランになっているが、窓側の席は満席だった。
房総半島だけど、暴走はしていないつもり。
帰宅したのは24時を廻っていた。車がカボチャにならなくて良かった。
三鷹を10時半頃出発して、高井戸から首都高速に入る。
レインボーブリッジを渡って湾岸線に入り、東京湾アクアラインの「海ほたる」で休憩。
東京湾アクアラインというのは、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ15.1kmの長さの自動車専用道路。川崎側の基点から9.8km地点にある海ほたるPAまでは海底トンネルになっており、海ほたるから海上に出て、木更津側は4.4kmに渡って東京湾上の橋になる。
海ほたるは東京湾に浮かぶパーキングエリアの名称である。
青く発光する体長3~3.5mmの甲殻類「ウミホタル」に由来する。
1階は大型車駐車場、2階は木更津方面からの車の駐車場、3階は川崎方面からの駐車場、4階・5階がレストランなど観光施設になっている。
1日ここで遊んでUターンして帰る人も多いという。Uターンの場合は片道料金になる。
5階の「木更津食堂」でお昼を食べた。
海鮮丼とうどんのセットで1780円。美味。
ここはPAだけあってアルコール類は無いが、キリンフリーが380円。
海を見渡せるレストランになっているが、窓側の席は満席だった。
鴨川シーワールドに行くつもりだったが、途中マッタリしすぎた為着いたのは3時頃。
東日本大震災の影響か4時で閉園するというので、シーワールドは止めて九十九里浜を見に行こうということになった。
途中立ち寄った勝浦海岸。
東日本大震災の影響か4時で閉園するというので、シーワールドは止めて九十九里浜を見に行こうということになった。
途中立ち寄った勝浦海岸。
九十九里浜に着くころに雨が降り出して、着いた時には土砂降りに。
苦渋九里浜。土砂だらけ。
雲竹斎の今日のウンチク
1里=4kmとすれば九十九里は396kmの長さになる。そんなに長い訳が無いのう。
実際の長さは約66kmなんじゃ。それでもすごい距離なんじゃが・・・
長さを強調する為に九十九里と表現したのかと思っていたんじゃが、ちゃんとした根拠があるらしいんじゃ。
昔々、源頼朝がこの浜に1里ごとに矢を立てさせたところ、99本の矢が立ったという伝承があるそうじゃ。
今の日本では1里=約4kmじゃが、1里の長さは国によって違うんじゃ。例えば中国では500m、朝鮮では約400mじゃ。
日本でも1里の長さは時代によって、地域(地形)によっても違っていたんじゃ。
源頼朝は1里=6町として命を出したと言う。1町=109.09mじゃから、
6町=109.09m×6=654.54mを1里として計算しておる時代じゃ。
654.54m×99=64799.46m=約65km!
バッチリ計算が合っておる。
百里浜としなかったところが粋じゃなぁ!
まあ、理屈をこねれば99本矢が立ったのならその間の距離は98里なんじゃがな。
細かい詮索は粋じゃないからのぉ。
長さを強調する為に九十九里と表現したのかと思っていたんじゃが、ちゃんとした根拠があるらしいんじゃ。
昔々、源頼朝がこの浜に1里ごとに矢を立てさせたところ、99本の矢が立ったという伝承があるそうじゃ。
今の日本では1里=約4kmじゃが、1里の長さは国によって違うんじゃ。例えば中国では500m、朝鮮では約400mじゃ。
日本でも1里の長さは時代によって、地域(地形)によっても違っていたんじゃ。
源頼朝は1里=6町として命を出したと言う。1町=109.09mじゃから、
6町=109.09m×6=654.54mを1里として計算しておる時代じゃ。
654.54m×99=64799.46m=約65km!
バッチリ計算が合っておる。
百里浜としなかったところが粋じゃなぁ!
まあ、理屈をこねれば99本矢が立ったのならその間の距離は98里なんじゃがな。
細かい詮索は粋じゃないからのぉ。











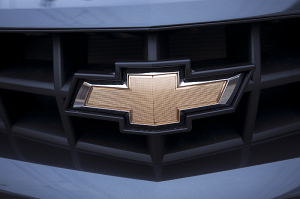












































最近のコメント